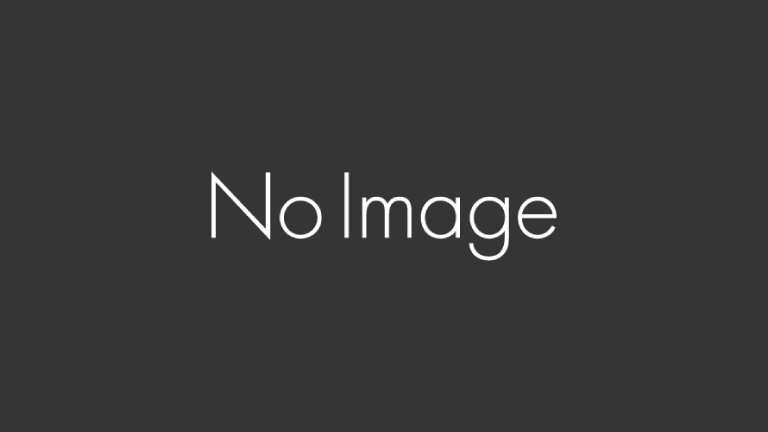先日(2019年1月12日)、金曜ロードショーで『耳をすませば』が放送されました。
1995年の公開から24年が経ちますが当時はもちろん、時代を経て尚この作品には本当に価値があると私は考えています。
なぜ私が『耳をすませば』に価値があると考えるのか、また価値とはどのようなものか、今回はそれについて書いていきます。
『耳をすませば』という作品と、公開された1995年という時代について。
公開当時の1995年はどのような時代であったか。
『耳をすませば』が公開された1995年当時、私はまだ10歳の子どもで、社会の大きな流れといったことをそれほど真剣に考えてはいませんでした。
しかし一方で、当時起こった大きな事件に対して「なにか大変なことが起こっているぞ」という感覚を持ち始めた時期でもありました。
1995年は日本にとって大きな出来事が2つあったと思います。
阪神大震災とオウム真理教の一連の事件です。
小学生であった私も、警察が麻原彰晃逮捕のために教団施設に捜査に入るという日には、まだその時間は学校にいましたが、先生に頼んで教室にあるテレビをつけてもらったお覚えがあります。。
この大きな2つの出来事そのものに対する評価は様々な専門的なものがあり、それに関して私は詳しく論評する知識も能力もありません。
しかしその当時に生き、社会というものはどのようなものかを考え感じ始めていた時期でありるので、その感覚を素直に言葉にしつつ考えることは、意味のあることだと思うのです。
そんな私には、その大きな2つの出来事があった1995年という年は、それ以降の時代の雰囲気を決定的なものにした年であるという確かな実感があります。
そしてその雰囲気とは、暗く重い雰囲気です。
95年から少しさかのぼり、日本は昭和から平成の初期にかけて、後に「バブル」と称される空前の好景気を謳歌していました。
しかし、1991年から1993年(平成3年から平成5年)にかけて景気は大きく後退し、後に「失われた10年」と呼ばれる不況が始まります。
95年当時にも、テレビ番組や音楽(J-pop)にはどこかまだ享楽的なバブルの名残を感じさせるものがありましたが、その経済状況をはじめ、その後続く日本の暗い雰囲気を決定づけた出来事が、自然災害である阪神大震災と社会的事件であるオウム真理教という認識です。
1995年とアニメ
そして、1995年当時その雰囲気を代表するような作品として現れた作品が『新世紀エヴァンゲリオン』です。
偶然なのでしょうが、社会の状況とそれを端的に表すような文化作品が同時に、時には時代を先取りして現れることがあります。
それが95年に関しては『エヴァ』だと思います。
『エヴァ』と時代や社会との一致、その社会的な意味合いについてはその当時から様々な評論家などが論じていたようですし、今でもエヴァは日本を代表するアニメであり続けています。
その多様かつ詳細な論評についてここでは述べることはできませんが、例えば批評家で作家の東浩紀さんは、当時から「デリダとエヴァを等価に語る批評家」と言われていたようなので、東浩紀さんの関連する著作を参照してみるのも面白いと思います。
また、1995年に放送されたアニメの一覧のリンクを掲載しておきます。
私はアニメにそれほど詳しいわけではありませんが、なぜアニメを取り上げるかと言えば、といえば、それがハイカルチャーであろうがサブカルチャーであろうが、文化はその時代を否応なく反映してしまうという性質があると考え、そしてむしろ、サブカルチャーのほうが「時代感覚」を率直に反映していると思うからです。
また何より、今この記事で主題にあげているのが『耳をすませば』というアニメ作品だからです。
そして、時代を代表するアニメである『エヴァ』に対応する当時の作品が『耳をすませば』だと私は考えます。
『エヴァ』と『耳をすませば』の時代性
『エヴァ』その時代の出来事や雰囲気を代表している作品であると言いました。
その魅力は、少年が搭乗するかっこいいロボット(便宜的にそういうことにしておきます)の戦闘やアクション、可憐な美女・美少女達、そして謎めいたストーリー展開など様々あり、それをそれぞれ好きなように楽しむことができ、エンターテイメント作品としても非常にレベルが高いと思います。
しかし、私が『エヴァ』におけるメインのテーマと考えるのは「主人公・碇シンジの成長物語と、その失敗と逃避」です。
『エヴァ』は、当初はそれまでの数あるロボットアニメ、または少年少女が主人公の古今東西の物語と同じように、「未熟な人間が困難を乗り越え成長していく物語」だったように見えます。
『漫画版エヴァ』の第2巻のあとがきにおいて、使徒のデザインに携わったあさりよしとお氏も「エヴァンゲリオンは実にオーソドックスなドラマである。ミもフタもない表現を使えば『シンジ君の成長ドラマ』とくることができる。なのに、なぜ皆さん普通の見方をしない!?」と語っています。
第1巻のあとがきでは、監督・脚本の庵野秀明氏も「4年間逃げ出したまま、ただ死んでいないだけだった自分が、ただひとつ、『逃げちゃダメだ』の思いから再び始めた作品です」とも言っています。
つまり、問題や困難に立ち向かう姿勢の中で生まれた作品であると言えるわけです。
しかし、『エヴァ』はそこには着地しませんでした。
アニメ版のラストは「僕は僕だ。僕でいたい。僕はここにいたい。僕はここにいてもいいんだ!!」というシンジ君のセリフにもあるように、一応はアイデンティティの確立と確認(=人間的成長)に至りましたが、それは「”真実”は人の数だけ存在する」(加持リョウジ)というように、数ある着地点の1つでしか無く、今なお未完のストーリーと同様にその結論の大部分はまだ宙ぶらりんの状態です。
その後制作された劇場版のラストにおいても、碇シンジは全ての生物の自我境界線である「ATフィールド」の解除という結末である「人類補完計画」をある程度主体的に回避する選択しますが、その結果は「気持ち悪い」(惣流・アスカ・ラングレー)というものです。
そして、2000年台に入ってから制作された『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』(2007年~)は、作品内の物語が始まったと設定されている2015年を現実が追い越しても、未だ結末に至っていません。
この『エヴァ』結末の着地失敗が何度も起こっている状況は、95年から現在に至る20年以上、バブル崩壊から考えれば30年近くも行き先の見えない日本の社会とも一致しています。
『エヴァ』が始まった95年当時は、庵野氏自身も、また日本社会全体も、その時抱えていた問題に立ち向かい、そう遠くないうちに何かしらの形での解決という結末を見据えていたと思います。
ですが、両方とも2019年の現在に至っても未だその先行きは見えず、それどころか、かつておぼろげにでも見えていた落とし所には、そこにたどり着くチャンスをことごとく逃し、抱えていた問題はより複雑化し、悪化していくばかりに見えます。
つまり、『エヴァ』はどこまでも失敗を繰り返す日本社会と「シンクロ」してきた作品なのです。
では、その『エヴァ』に対する『耳をすませば』はどのような作品でしょうか。
誤解を恐れず言えば、『耳をすませば』は内容的に非常に小さな作品です。
物語の筋は単純に中学生同士の淡い恋愛物語であり、同じスタジジブリの宮崎作品や高畑作品と比べても、そのテーマに広く深い社会的な問題(例えば痛烈な文明批判とそれに対する自然霊崇拝など)が設定されているようには僕には見えませんし、なにより『エヴァ』と比比較しても、偶然にしろ、当時の社会背景や時代状況を重く背負い反映した作品ではなありません。
しかし、だからこそ貴重で価値がある作品だと私は考えます。
先にも述べたとおり、1995年は時代が日本に落とし始めた影が色濃くなった時期で、意識的にしろ無意識的にしろ、それを強く反映したのが『エヴァ』です。
それに対して『耳をすませば』は人間の普遍的な悩みを描いているとは言えますが、あくまでそれは個人的な不安や悩みであり、社会的なものではありません。
話の展開もオーソドックスな若者の恋愛物語で、途中暗雲立ち込めるシーンもありますが、それは受験や恋愛といった、やはり社会の中の個人の話にすぎません。
つまり、当時の現実社会に蔓延し始めた暗い空気はもちろん、物語の中においてさえ、その作品内の空気が反映されてないどころか、作品を見ただけではその社会がどのような社会なのか判然としません。
それどころか、実在の風景をモデルとしながら、すなわち当時バブルが崩壊し、不況の嵐が吹き始めていた東京の街すらどこか非現実的な、美しい風景にしてしまっているのです。
ラストシーンではそんな暗い雰囲気が立ち込め始めた、東京の街をバックに将来を約束する世間知らずな少年と少女が描かれています。
ですが、そのように暗い社会状況に無頓着な作品だからこそ、逆説的に重要な作品となっていると私は考えます。
『耳をすませば』の時代に則した価値と時代にとらわれない価値
繰り返しますが『耳をすませば』は、その後の経済的に後退し、多くの問題が露見する時代の端初に立ちながらも、そのような背景から切り離され、暢気で、ある意味牧歌的な世界観を持った物語です。
だからこそ、暗い時代のアンチテーゼとして意味があると考えます。
しかし、それだけではありません。
「暗い時代だから明るい物語が求められ、それに合致した」といった単純な理由だけがこの作品の魅力ではないと思うのです。
多分に想像を含みますが、私は以下のように考えました。
当作品の監督である近藤喜文氏はもちろん、なにより絵コンテを務めた宮崎駿氏をはじめスタジオジブリが、当時の後退し始めた社会とその少し前の行き過ぎた好景気バブル経済という状況にあり、それに対してなんの考えも持っていないということはありえないと思います。
そして、どんなクリエイターでもそうですが、その人が優秀であればあるほど「時代を背負う」ということが起こります。
そういった意味では『エヴァ』は正にそのような作品ですし、『耳をすませば』もそうだと思うのです。
ですが、もう少し違いを見出すとすれば、「『エヴァ』は背負ってしまった」のに対し「『耳をすませば』は背負い直した」作品であると思います。
「背負い直した」というのがどういったことかというと、時代の重みをそのまま受け止めるのではなく、それがどのようなものかを感じた上で、その中で人間として立っているためには何が必要かを考え、それを担い、示したということです。
当時の経済狂乱とも言える時代の中で、例えば宮崎駿氏や高畑勲氏が監督の作品を作っていたらどのようなものになっていたでしょうか。
僕は当時の社会状況に対する立場を示した、文明批判などのもっと直截的な作品になったと思います。
実際に95年当時すでに制作が始まっていた宮崎氏の『もののけ姫』(97年公開)は言うに及ばず、『耳をすませば』の前年である94年に公開された高畑氏の『平成狸合戦ぽんぽこ』は、時代もモデルとなった舞台もほとんど同じにしながら当時の社会や文明に対する(どちらかといえば批判的な)立場が色濃く反映されています。
それに対して『耳をすませば』の文明に対する態度はどうかというと、それほど明確ではありませんが、私は少し肯定的なものだと感じます。
ただ、それは文明に対して賛成と反対という二項対立においての賛成の立場というのではなく、人間の営みを、その流れが緩やかで抗いがたいものである限り、ありのままに受け入れるといった意味での肯定です。
それは雫の小説と聖司のヴァイオリンなど、書物や音楽に対する夢や憧れ、地球屋の主人の職人という生業と、それらを「作る」という活動に対する畏敬の念が見て取れること点であり、ある意味で物語の中心である「バロン」もまた、「人間に命を吹き込まれたもの」であるという点です。
また他にも、電車やそれに乗って「通勤」する猫や自嘲を含みながらも明るく笑いながら「コンクリートロード」を歌う姿にはそれを感じます。
一方で、図書館のシステムが図書カードからバーコードに移行することについては寂しさを感じるといったバランス感覚です。
つまり、時代に対して対立するのではなく、その抗いがたい流れに乗りながらも、率先して先頭を走っていくのではなく、変化を受け入れながらもゆっくりと自己の感覚を確かめながら、流れの後ろの方をついていくといった態度です。
このような感覚と態度こそが『耳をすませば』という作品の価値だと私は考えます。
そしてこれは、近藤喜文監督だからこそ表現できたことだと思います。
宮崎氏や高畑氏にはバランス感覚が無いという意味ではなく、それどころか両者とも繊細で非常に優れたバランス感覚を持っていると思います。
しかしこの2人は、そのバランスの中で逡巡し苦悩する人間といったものを描いた時、その魅力を発揮するタイプだと思います。
それに対して、近藤氏はどこまでも「普通」です。
この「普通」とは、人間の自然な生活・営みと、それに対する暖かな眼差しを持っているということです。
問題や困難に立ち向かい、迷い、悩みながら歩みを進めていくというのはもの凄く力強い人間のあり方であり、貴重で素晴らしいことだと思います。
それは宮崎駿氏、高畑勲氏、そして庵野秀明氏の態度であり作品で、だからこそ彼らの作った作品がいつも強烈な魅力と影響力を持つのです。
特に、95年当時から現代に至る影の色が濃く、困難な時代においては強く求められる態度です。
しかしそのような態度・生き方は厳しく過酷なもので、いつでも誰にでもできるのもではありませんし、できる人間でさえ、自分をすり減らしながら歩んでいくことになります。
ですが近藤喜文氏は、立ち向かい自己をすり減らしながら生きていくのではなく、その時の状況を含め、自分が生きているという人間の基本的な条件を確認・受容した上で、どんなあり方が望ましく自然なものかの理想のあり方の1つを示したということです。
そして、そのようなあり方は困難な時代の中で見失われがちだからこそ、『耳をすませば』が価値を持つ、つまり時代に則した作品であると言う事ができ、同時にそこにおける人間の姿はいつの時代においても普遍的な、つまり「普通」であり時代にとらわれない作品だと言えるのです。
つまり『耳をすませば』は、1995年当時はバブルが崩壊し阪神大震災やオウムの事件が起こり、現在まで続く不穏な時代に入った時代であり、その時放送されたアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』とは違った方向で時代に求められた作品であると同時に、提示したものはその時代だけではなく、いつの時代にも追求される希望だと考えるのです。
これが『耳をすませば』の”時代性”と”非時代性”という意味です。
まとめ 『耳をすませば』困難が続く時代でも色褪せない物語
近藤氏は昭和から平成にかけて激しく揺れ動く時代に、スタジオジブリという環境に身を置きながら、大きな社会のうねりや問題を認識していなかったはずはないと思います。
ですが、それに立ち向かうというやり方だけでなく、どれだけ普通の生活が保つことが、もしくはもっと踏み込んでそれを守りたいという想いを持ち、そのために望ましいあり方・理想を示したのです。
そしてそれを表現し、作品としてあの時代に結実したのが『耳をすませば』だと私は考えます。
『耳をすませば』一見したところ、小さく暢気な作品です。
しかしその価値は、激しく困難な時代における癒やしや逃避といった消極的なものではありません。
将来や恋に悩み成長するという「普通」で、だからこそ尊い、しかし時代の中で見失いがちな人間のある意味で本質的かつ希望に満ちたあり方を、堂々と謳い上げた点にあるのです。
それは公開から20年以上経った現在でも色褪せていません。
24年前の作品を理想としそれに倣うことは、ある点では退行を意味するかもしれません。
ですが『耳をすませば』が当時示した希望を再確認し、個人の1つの行く先として考えることは、この先行きの見えない、ともすれば人間一人ひとりの人生が軽んじられる時代において意味を持つのではないかと私は考えています。