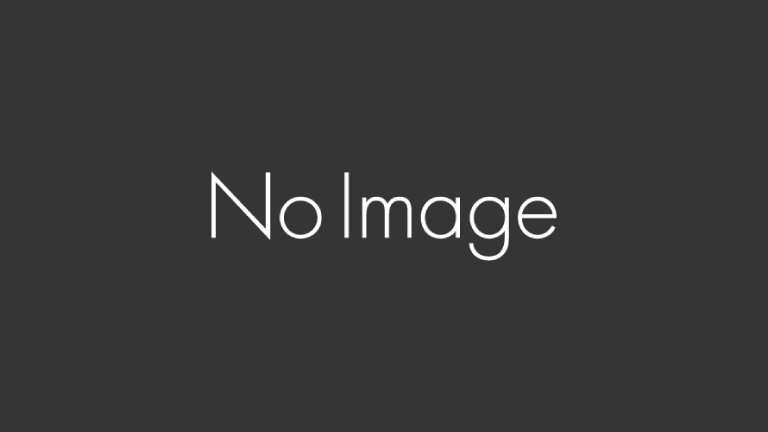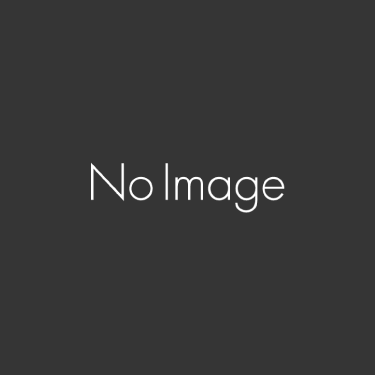私は大学生の頃から本格的に旅行をするようになった。
様々な土地に出かけては、カメラやスマホで写真を撮りながら歩いている。
だが旅行に行き始めた頃は「できるだけ身軽がいい」という、やや格好つけた考えから、カメラなんて持っていくことはなかったし、スマホすら家に置いて出かけていた。
だから私には、「写真には残っていない旅の思い出」というものがいくつもある。
これからは忘備録も兼ねて、そんな思い出を少しずつ書き綴っていきたいと思う。
私が生まれたのは港区の病院で、私が持っている最も古い記憶は2歳の頃、当時の住まいであった新宿区の雑居ビルの一室である。
それから3歳の時、都内の下町の方に引っ越すことになった。
以降現在に至るまでそこが実家となるが、高校は都心のビルに囲まれた学校に通った。
私にとっては東京のビル群が原風景であり、そこに憧れを抱いていたため、場所で学校を選んだのだ。
高校生の頃は遠くに出かけることはなく、渋谷や新宿といった大きな街はもちろん、城東地区や多摩地区など、都内の様々な地域をよく歩いた。
前置きが長くなったが、その後、日本の様々な風景を求め、本格的に旅行に行くようになった。
目的地は定めず、御茶ノ水から中央線に乗り込んだ。
都心から西に向かうと、慣れ親しんだビル群がどんどん遠くなり、武蔵野の穏やかな住宅街が車窓を占めるようになる。
そこはまだ「都会」の空気を感じる。
しかし立川を出発し浅川を渡り、八王子に到着すると、街こそ栄えているが山も近づき、「地方の趣き」が出てくる。
さらに西に進み高尾に到着すると、「東京」のイメージから一変する。
そして高尾で、都心のど真ん中を通り抜ける銀の車体にオレンジ色のラインの入った車両から、「甲府」「小淵沢」などの行き先が示された、青色のラインが入った車両に乗り込むと、一気に旅情が湧き上がる。
その時乗った小淵沢行きの車両は、運良くクロスシートだった。
乗客が少なければプライベートな空間となり、車窓の風景を眺めたり、本を読んだりと、自分の世界に浸ることができる。
到着した先で名所旧跡、景勝地や見知らぬ町を巡るのも良いが、こんな移動時間も、最も楽しい旅のひとときである。
特に高尾から甲府盆地までは、中央線でも美しい景色を楽しめる区間であり、旅への期待が高まっていく道のりだ。
だがそのときはそうはならなかった。
持ってきていた文庫本に、読むでもなく視線を落としていると、前方のクロスシートから視線を感じた。
ふと顔を上げてみると、背もたれから小さな女の子が顔を出していた。
目が合うと、恥ずかしそうに顔を引っ込めた。
本に視線を戻すと、また視線を感じる。
また見ると、また隠れる。
それを何度か繰り返すと、女の子は段々と、笑いながら隠れるようになった。
女の子が何をしているかに気づいたのか、母親らしい若い女性が「やめなさいと」女の子に注意しながら立ち上がり、私に向かって「すみません」と謝った。
だがそれでも女の子はやめようとしない。
ひょっこりと顔を出し、満面の笑みでこちらを見ては、目が合うと隠れる。
とても可愛らしい笑顔の女の子だった。
私も嫌な気はしなかったので、女の子がこっそりと顔をのぞかせた時、変顔をして対抗してみた。
すると思いの外良い反応をしてくれて、キャッキャと声を上げて笑い始めた。
それを見たその子の母親は先程より強く注意をし、再び私に謝った。
しかし女の子は止まることはなかった。
今度は女の子が変顔をして現れた。
それに対し私も変顔で応じる。
彼女のテンションはどんどん上っていった。
ついには私の方の席へ直接やってきた。
その様子に母親も慌ててこちらへ来て、申し訳無さそうに謝りながら女の子を連れ戻していった。
しかしそれでも懲りない女の子はこちらへやってきて、私に話しかけてきた。
流石に困惑する母親に「いいですよ」と言うと、相席することになった。
女の子は「ゆゆちゃん」といい、2歳だそうだ。
母親は私とほとんど年齢は変わらなかった。
お互い自己紹介をすると、母親も申し訳無さだけではなく、私という見知らぬ男への警戒心も薄れたようで、これからの行き先など、取り留めもない雑談を楽しんだ。
2人は清里へ行く予定だという。
現地で友人と落ち合うらしかった。
大人同士で会話をしていると、ゆゆちゃんが割り込んできた。
手にはスマホを持っていた。
最近お気に入りの動画を私に見せたいらしい。
母親も困惑していたが、子どもを放っておく訳にはいかないと、ゆゆちゃんと動画を見ることにした。
可愛らしいキャラクターが映っていて、それをゆゆちゃんが説明してくれる。
正直なところ、小さな子どもらしい支離滅裂な説明は、何を言っているのかほとんど理解できなかったが、彼女が楽しそうにしている様子に、私も楽しくなっていた。
その後も動画を見たり、最近覚えたという「ずいずいずっころばし」で遊んでいると、あっという間に小淵沢に着いた。
乗っていた電車の終点であるため、清里へ向かう彼女たちと一緒に下車する。
するとゆゆちゃんは私の手を取り「一緒に行く」と言い始めた。
私は目的地を決めていなかったため、清里へ向かう小海線に乗っても良かった。
だが彼女たちの旅行を邪魔するわけにも行かないし、流石に呆れ顔の母親を見て言った。
「ぼくはあっちへ行く電車に乗るから、ここでバイバイだね」
ゆゆちゃんは少し駄々をこねたが、母親が「お兄ちゃんは行けないの」と言うと、渋々私の手を放して、「バイバイ」と手を振った。
母親も「ありがとうございます」と言いながら、反対のホームへの階段を降りていった。
私はその後中央線を乗り継ぎ、長野県の松本でその旅行の1拍目の宿を取った。
起こった出来事はそれだけだ。
もう随分前のことだが、楽しい旅の記憶として、今でも時々思い出す。