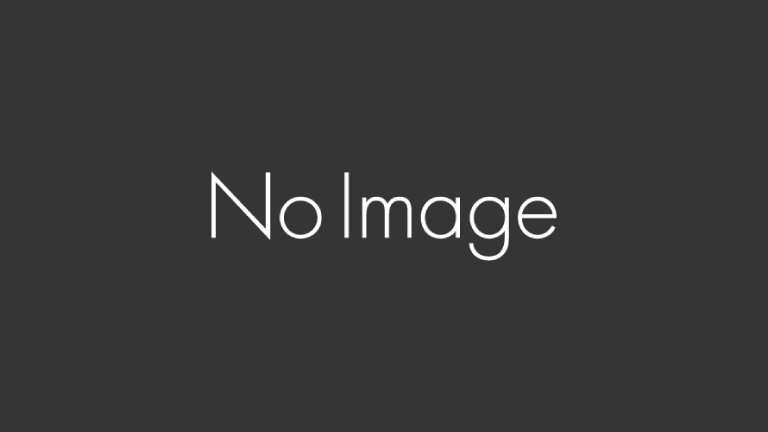上野の美術館で同時期に開催していたルーベンスとムンクの展覧会を両方観てきました。
ルーベンスとムンクは時代も作風も全く異なる画家ですが、同時期に観て比較することで感じ、考えたことがあるので、それについて書いていきたいと思います。
ルーベンス展とムンク展を観て、比較して考えたこと。
私は気が向いた時、美術館や博物館に行くくらいには芸術は好きなので、学芸員の資格も持っています。
今回はルーベンスとムンクがほぼ同時期に上野で展覧会をやっていたので両方観てきました。
そこで感じたこと、考えたことを書きたいと思ったので記事にしてみます。
結論から言いますとどちらも凄い作品ばかりでしたがですが、ムンクのほうが気持ちよく楽しめました。
その「気持ちよさ」の理由を探っていきます。
ルーベンスとムンクの概要
フルネーム・生年あたりをWikipediaから引用しておきます。
ルーベンス
ピーテル・パウル・ルーベンス[1](蘭: Peter Paul Rubens オランダ語: [ˈrybə(n)s]、1577年6月28日 – 1640年5月30日)は、バロック期のフランドルの画家、外交官。祭壇画、肖像画、風景画、神話画や寓意画も含む歴史画など、様々なジャンルの絵画作品を残した
ピーテル・パウル・ルーベンス – Wikipediaより
ムンク
エドヴァルド・ムンク(Edvard Munch (ノルウェー語: [ˈɛdvɑʈ muŋk]), 1863年12月12日 – 1944年1月23日)は、19世紀 – 20世紀のノルウェー出身の画家。『叫び』の作者として世界的に有名で、ノルウェーでは国民的な画家である
エドヴァルド・ムンク – Wikipediaより
付け加えることとしては、ルーベンスは日本ではアニメで有名な『フランダースの犬』でラストの場面でネロが観たがっていた絵の作者として知られています。
ネロとその愛犬パトラッシュはそのルーベンスの絵画の前で天に召されます。
ムンクはなんと言っても『叫び』の作者として知られています。
両者とも芸術史上に燦然と輝く超有名芸術家ですので、細かい知識はなくとも単純に「観ておくべき」芸術家と言えるでしょう。
ルーベンスの作品は観ていてすごく疲れた
ルーベンスとゲーテ
私にとってルーベンスは特別で、ぜひ観たい芸術家です。
なぜなら私が大好きなドイツの大作家ゲーテが、ルーベンスのその天才性について明朗に語っていたからです。
それを読んで以来、観る機会があるとわかったらできる限り足を運んでいます。
ではまず、そのゲーテが語ったルーベンスに関する話を紹介します。
ゲーテはその晩年に交流を持っていた若者エッカーマンに対して、ルーベンスの風景画を観ながら、その絵が自然光を描いているだけでなく、意図的に不自然な光を描くことにより人物を強調しているという指摘して、ルーベンスの天才性について語っています。
「芸術家が、」とゲーテは続けた、「忠実かつ敬虔に、自然をその隅々まで模倣しなければならないことは、もちろんだよ。動物を描くにしても、その骨格、脚や筋肉の状態を勝手気儘に変えて、本来の特徴をそこなうようなことは、ぜったいに許されないことだ。なぜなら、それは、とりもなおさず自然を破壊することだからだ。けれども、一段と高い域に達した芸術家は、一枚の絵をほんとうの絵にする方法を心得ているから、もっと自由に描くことができる。こうなれば、ルーベンスがこの風景画において二重の光を使っているように、虚構の世界へ足を踏み入れてもかまわないのだ。
エッカーマン『ゲーテとの対話(下)』岩波文庫(1969年、山下肇訳)p.137
「忠実かつ敬虔に、自然をその隅々まで模倣しなければならない」
私はこの話が大好きで、絵画を含め、ほとんどすべての創作活動に通じるのではないかと思っています。
レオナルド・ダ・ヴィンチも「遠近法と解剖学を学べ」と言っているし、ピカソも写実が抜群に巧いのは知られており、その上であのようなキュビズムなど「虚構の世界」を試みています。
他にも、手塚治虫もマンガでのデフォルメが凄いだけでなく、描く虫の絵は実物のようです。。
日本には「守破離」という考え方がありますが、「守」つまり、まず守るもの、模範とするものは、この場合、自然とそのあり方です。
もちろんその自然には人間も含みます。
この基本ができているクリエイターの作品は、フィクションでも現実に迫った、または現実を超えるような力強さがあると感じます。
ちなみに、ゲーテは文筆を始め多彩な仕事を成し遂げていますが、すべての活動においてこうした本質的な基本を大事にしています。
そして、そのようなゲーテの考えや姿勢がふんだんに読み取ることができる、エッカーマンの『ゲーテとの対話』は、現代の様々な分野のできるだけ多くの人が読むべき本だとぼくは思っています。
ニーチェや水木しげるも座右の書としていたようです。
Amazon.co.jp: ゲーテとの対話 全3冊セット (岩波文庫) : エッカーマン, 山下 肇: 本…
ルーベンス展は良かったけど疲れた
以上のように、ルーベンスの風景画についてゲーテは語っていました。
ですが今回私が訪れたルーベンス展では、風景画はほとんどありませんでした。
行く前に展覧会情報を確認していなかった私が悪いのですが、今回は「バロックの誕生」というコンセプト、つまり宗教などの壮大なテーマで描かれた作品が中心に集められたものだったのです。
社会や宗教をテーマにした作品が多く、人物が多く描かれたものがほとんどです。
もちろん、一つ一つの作品は圧倒的に優れていることはわかりますし、おそらく誰が観ても「すごい!美しい!」となるものばかりでした。
しかし、そこにあった作品はとにかく人間にしろ神話上の存在にしろ「肉体」ばかりだったので、それに私は食傷気味になり、疲れてしまったのです。

それでは、ルーベンスの作品がの何が私を疲れさせたのか説明します。
上のキリストの絵を観てもわかるように、その描かれた肉体は見た目も筆致からも、とにかく肉感的で「充実」しているということです。
ヘラクレスなんてもう筋骨隆々のムキムキでした。
そんな「充実した肉体」ばかりを観ていると、そればかりで単純に飽きたということではなく、観ていくに連れて違和感がどんどん強くなっていきました。
その「違和感」がなにかというと、ルーベンスが描いた肉体を見て「人間の体ってこんなキレイなものばかりか?」と感じたことです。
描かれた肉体には、それが死体であっても、確固とした存在感がありました。
もちろん、芸術ですから描くのはその対象も描き方もできるだけ「美しく理想的であるように」ということはあるでしょうが、それを踏まえても、描かれている肉体の「充実感」に、ぼくは「くどすぎる」と感じてしまったのです。
そして、その「くどさ」がどこから来ているか考えてみました。
まず、時代による価値観です。
例えば、ヨーロッパで中世から近世に描かれている裸婦像は、現代のファッションモデルと比べれば「太っている」と感じるほど肉感的で、当時はそれが良いとされていたということです。
ですが、それだけではなく、私が考えるのは当時のヨーロッパでの「人間とその肉体に対する信頼感」です。
「肉体」についてはいろいろな解釈があると思いますが、この「人の形をした実態」というのは特別なものであったと思います。
たとえば「受肉」とはキリスト教において特別な意味を持ちます。
そして「受肉」という言葉を出しましたが、当時の宗教観も影響しており、キリスト教がどういったものかの宗教にかかわる議論はここでは別として、今回の展覧会は、宗教画では天使などの神的な存在はほとんど人間の形をして描かれていました。
日本では神の使いだけでなく、神そのものが動物の姿をしているという文化も不思議な事ではないですが、例外もありますが当時のヨーロッパでは、人間というのはその他の動物と比べて上位の存在と考えられていたと考えるのです。
それがルーベンス絵画に如実に出ていて違和感を感じたと考えるのです。
また上にも書きましたが、絵画を描く時「理想化される」ということも関係していると思います。
絵画に限らず、芸術は「理想を追い求める」という傾向にあり、例外もありますが、とにかく「良い(善い)もの」を表現しようとします。
それは作品制作において当たり前のことではありますが、そうして表現された理想的な人間像を観て、人々はいつの間にかそれが「人間の本質」であり、「自分たちにもそれが秘められている」と勘違いしてしまったのではないかと考えたのです。
つまり、宗教的に人間中心主義的な傾向があったのが、芸術によって表現された理想的な人間像を観ることによって、その「作られた」素晴らしさが自分を含む人間の本質と思うようになり、人間に対する信頼感に拍車をかけたのではないかと考えました。
私は文化や文明に触れると、人間というのは優秀な生き物だと思いますが、上記の「人間に対する極端な信頼感」は行き過ぎだと感じます。
つまりルーベンスの極端に理想化された人間の姿は、本質からズレてしまっていると感じるのです。
それはムンクの作品を観て、より強く感じました。
ムンクを観たあとは心地よい疲れが残った
ムンクが描く「不安」の正体
ルーベンスと比較したときのムンクを、私がどう考えたのかを書いていきます。
ムンクはルーベンスよりかなり後世の画家です。
時代が違うということは当然価値観やものの捉え方も大きく変わり、芸術家それぞれの考え方やトレンドもありますが、作風もだいぶ変わってきます。
ルーベンスであればその作品に込められた様々な意図や意味は別として、ひと目見て「美しい」と感じる方も多いと思います。
しかし一方、ムンクの『叫び』を観て、なんとも言えない魅力を感じることはあっても、多くの人は「美しい」とは感じないのではないでしょうか。
それどころか「不気味」や「不安」という負の感情さえ湧いてくるのではないかと思います。

絵画の解釈について、私は決めつけたり断定的なことを言ったりすることを好みません。
しかし、この『叫び』について「生や人間存在の不安を表現している」などと言われることがあり、それは1つの解釈として正しいと思います。
というのも、「人間とその肉体に対する信頼感」に支えられたルーベンスの作品とは異なり、ムンクの作品はこの『叫び』を含め、人間もそれを取り囲む世界も明確な形を持っては描かれていないものが多いからです。
ムンクは人間の生命や肉体は絶対的なものではなく、むしろ死をいつでも近くに感じ、儚く消えていってしまうものと考えていたのではないでしょうか。
特に形ある肉体についてはそう考えていたと思います。
これは、子供の頃に家族を病気で亡くしたというムンクの個人的な体験に由来するとも言えますし、時代によるとも言えます。
そういった「人間は絶対的でない」という感覚がムンクの「不安」の正体だと思います。
ムンクとニーチェ
私が今回の展覧会で初めて知って驚いたとともに、すごく納得したことがあります。
それはドイツの哲学者ニーチェをムンクが描いていたことです。
ムンクはこのニーチェの思想に共感していたそうです。
ニーチェの有名な言葉に「神は死んだ」というものがあります。
この言葉の意味や解釈は幅広く様々あると思いますが、今回の記事に絡めて僕なりの解釈を言わせてもらうと、「(キリスト教的)神はもはや人間の存在理由にお墨付きを与えることはない」ということ、つまりそれまで宗教教義に従い「人間はこうすべきだ」として行動してきたことや、その中で信じられてきた「人生の意味」などは無いということを明らかにしてしまったということです。
それまでの時代は、人間の生命や存在そのものは確かな意味があり存在しているとされていました
それは「神に与えられた」ものであり、人間の支えとなっていました。その表れがルーベンスの描く「肉体の充実感」であり「信頼感」です。
しかし、それはニーチェの「神は死んだ」の宣言により終わりを告げ、「人間存在は不確かなもの」となり、さらには「世界そのものの目的」というのも虚構であることが暴かれたのです。
おそらくムンクは個人的な経験からもそのことに気づいていたと思います。
ですからムンクの描くものは人物にしてもその目や鼻、輪郭は曖昧であり、空や風景は歪んでいます。そしてそれを観る者にも不安を与えると私は考えるのです。
私はそのような「人間の本質的な不安」が描かれたムンクの作品が好きです。
好きというだけでなく、ルーベンスを観ていたときのような違和感はなく「すごくしっくり来る」「腑に落ちる」といった感覚です。
つまり、ムンクの作品の方が人間や世界の「不確かさ」という本質を見抜き、正確に表現しているとかんがえるのです。
だからルーベンスの時のような違和感はなかったので、心地よい疲れでした。
それにムンクはそういった不安を感じさせるような作品だけでなく、明るく力強い作品も数多く描いています。
展覧会のコンセプトにもよりますが、今回のムンク展は、ムンクの人生の歩み全体にスポットを当て作品を展示していたので、ムンクがその時々にどういった経験をして、どういった考えを持つようになり、そしてどうのように作品を作っていったかということもしっかりと観ることができました。
そして、そのムンクの描く作品と人生というものは、正に「人間の姿そのもの」とだと私は感じ、ルーベンスよりより本質的だと考えるのです。
まとめ ムンクのほうが真実を描いている
ルーベンス展もムンク展もその展示と作品はどちらも素晴らしいものでしたが、私の今の感性に適い感銘を与えたのは、今回はムンクの方でした。
ルーベンスの作品も素晴らしく、感動しましたが、ムンクのほうが「世界や人間の真の姿を描き」、心に迫ってくるものがありました。